野に咲く花
2020.09.17
カテゴリ:田舎暮らし
タグ:山梨県北杜市/日々のこと
散歩の時に見かけた野に咲く花の名前を調べ見ました。

『イヌタデ』
見慣れた雑草ですが、よく見てみるとピンクの粒粒が可愛い。
おままごとで、この花をバラバラにしてご飯に見立てたことから、
アカマンマという別名がついたとか。確かに、米粒みたいに見えます。

『カタバミ』
ハートの形の葉が、まるでクローバーみたい。
黄色の花は日が当たる日中に咲き、夜や曇っている時は閉じてしまうとか。
可愛い見た目と違って、深く根を張って駆除が大変な雑草らしいので、
庭に生えてきた場合は要注意です。

『ゲンノショウコ』
漢字で書くと『現之証拠』。
薬草として江戸時代の初め頃から用いられてきたそうで、
服用するとたちまち効き目が得られたことから、その名がついたとか。

『野紺菊(ノコンギク)』
ノコンギクとヨメナでどちらなのか、見分けが難しい。
葉の手触りで比べるのが一番見分けやすい方法だとか。
ノコンギクの葉→ザラザラ
ヨメナの葉→ツルツル
葉を触ってみたら、葉の両面ともザラザラ!なので、これはノコンギク。

『待宵草(マツヨイグサ)』
待宵草と月見草は、同じマツヨイグサ属の植物。
「富嶽百景」で太宰治が「富士には月見草がよく似合ふ」と描写した月見草は、
「黄金色をした」という表現からこの待宵草だったのでは、と言われているそうです。

『ニラ』の花
観賞用のハナニラではなく、食べられるニラに咲いた花。
ちょっと散歩したら、可愛い花にたくさん会えました(^^♪

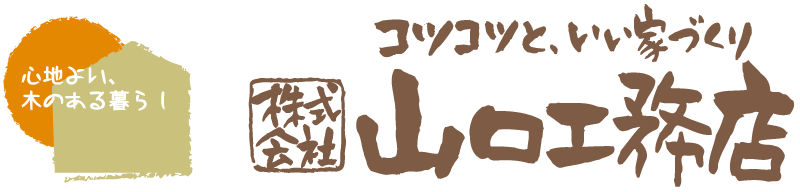




コメント